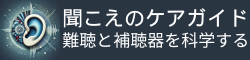「最近、会話が聞き取りにくい」「テレビの音量を上げないと聞こえない」と感じることはありませんか?そのようなとき、多くの方が「補聴器」や「集音器」の購入を検討されるかもしれません。しかし、これらの違いを正しく理解していないと、自分に適した製品を選ぶのが難しくなります。本記事では、補聴器とは何かを詳しく解説し、集音器との違いや選び方のポイント、補聴器が医療機器である理由についてもご紹介します。
補聴器とは何か?
補聴器の定義
補聴器は、難聴などで聴力が低下した方が音を聞き取りやすくするための医療機器です。個々の聴力や生活環境に合わせて調整し、音声の明瞭度を高めることで、コミュニケーションの支援を行います。
集音器との違い
- 法的な分類
- 補聴器:医薬品医療機器等法(旧薬事法)に基づく管理医療機器です。品質や安全性、性能について厳しい規制と管理が行われています。
- 集音器:一般的な電気製品として扱われ、医療機器ではありません。
- 調整の有無
- 補聴器:専門家による精密なフィッティング(調整)が必要です。個々の聴力データに基づき、周波数ごとに音量や音質を細かく設定します。
- 集音器:一般的に音を単純に増幅するのみで、個々の聴力に合わせた調整はできません。
- 機能と性能
- 補聴器:雑音抑制、ハウリング防止、指向性マイクなど高度な機能を備えています。
- 集音器:基本的な音の増幅機能のみで、周囲の雑音もそのまま増幅されます。
補聴器はなぜ医療機器なのか?
難聴は身体の病気
難聴は、内耳や聴神経などの障害による身体的な疾患です。補聴器は、この難聴によるコミュニケーション障害を補うためのリハビリテーション用の機器であり、身体に装着するため医療機器として分類されます。歳を取ると多くの人が難聴になりますが、多くの人がなる=当たり前、と考えて何の行動もしないと、認知症を発症するリスクが高まる恐れがあります。
効果の面
- 個別調整の必要性:一人ひとりの聴力は異なり、特に周波数ごとに聴こえ方が違います。補聴器は、専門家が個々の聴力に合わせて調整することで、最適な音質と音量を提供します。
- 周波数ごとの音量と音質の調整:人間の耳は、低音から高音までの周波数ごとに感度が異なります。補聴器では、各周波数帯における聴力の状態に合わせて、音量を細かく調整します。例えば、高音域の聴力が低下している場合、その周波数帯の音を重点的に増幅します。また、音質の調整とは、特定の周波数帯を強調したり抑えたりすることで、言葉の明瞭度や音の自然さを最適化することです。これにより、言葉の聞き取りやすさが向上し、快適な音質が得られます。
安全性の面
- 音響外傷のリスク:不適切な音量設定は、音響外傷を引き起こし、難聴を悪化させる可能性があります。
- 装着によるトラブル:補聴器の装着により、耳周囲の皮膚炎や外耳道炎などのリスクがあります。
- 耳型採取のリスク:耳型採取時に異物が残るなどの危険性もあり、専門的な知識が必要です。
治療の一環として
補聴器の使用は、難聴の治療やリハビリテーションの一環であり、医療的な効果を発揮するため、医療機器として厳しい基準が設けられています。
補聴器の特徴
フィッティングの重要性
- 個別の聴力データに基づく調整
- 聴力検査の結果をもとに、専門家(認定補聴器技能者や言語聴覚士)が周波数ごとに音量や音質を細かく調整します。
- 具体的な音質調整の内容:例えば、特定の周波数帯で音が強すぎると不快感を与える場合があります。そのため、その周波数帯の音を適切に抑えることで、聞き心地の良い音質を実現します。また、言葉の聞き取りに重要な周波数帯を強調することで、会話の理解度を高めます。
- 他人の補聴器は合わない
- 個々の聴力は異なるため、他人の補聴器を使用しても効果が得られず、逆に耳を傷つける可能性があります。
フィッティング方法の種類
- 専門家によるフィッティング
- 認定補聴器技能者や言語聴覚士(ST)が行います。
- 詳細な聴力検査とカウンセリングを通じて、最適な調整を行います。
- セルフフィッティング
- 専門家によるフィッティングができず、ユーザー自身がスマートフォンアプリを使って、自分自身の匙加減で簡易的に調整するものがあります。
- 同様に専門家によるフィッティングができませんが、スマートフォンアプリ内で聴力測定を行い、その結果に応じてプログラムが調整を行うものもあります。
- いずれも専門家のサポートがないため、適切な効果が得られない場合があります。
フォームファクターとバッテリーライフ
補聴器の形状(フォームファクター)
補聴器にはさまざまな形状があり、生活スタイルや好みに応じて選ぶことができます。主なタイプは以下の通りです。
- 耳かけ型
- 耳の後ろに本体を掛け、チューブやドームを通して音を伝えます。
- 操作が簡単で、装用感が安定しています。
- 耳あな型
- 耳の穴の形状に合わせて作成され、外から見えにくいデザインです。
- 小型で目立たないですが、補聴器本体の操作という意味ではやや難しい場合があります。最近はアプリで操作することも可能なので、気にならないかもしれません。
補聴器のタイプについて詳しく知りたい方は、以下のサイトをご参照ください。
バッテリーライフ
- 電池式
- 空気電池を使用し、約5〜10日間使用可能です。
- 電池交換が必要ですが、連続使用時間が長いです。
- 電池交換はやや細かい作業になりますので、煩わしさを感じる方もいらっしゃいます。
- 充電式
- 専用充電器で充電し、1回の充電で約16〜24時間使用可能です。
- 電池交換の手間がなく、環境にも優しいです。
アプリでできること
スマートフォン連携
近年の補聴器は、スマートフォンと連携してさまざまな機能を利用できます。
- 音量調節
- アプリを使って左右の音量バランスを調整できます。
- 音質調整
- 高音域や低音域の強調など、細かな音質設定が可能です。
- 指向性の設定
- 前方の音を強調する、周囲の音を均等に取り込むなど、聞きたい音にフォーカスできます。
- プリセットの選択
- 会話モード、音楽モード、騒音下モードなど、シーンに合わせた設定を簡単に切り替えられます。
- バッテリー残量の確認
- バッテリーの状態をアプリでリアルタイムにチェックできます。
アプリ以外でのコントロール
- 補聴器本体のボタン
- 音量やプログラムの切り替えが可能です。
- タップコントロール
- 補聴器を軽くタップすることで、電話の応答や音楽の再生・停止などが行える機能です。
値段
補聴器の価格は大きく異なり、消費者にとって混乱の元になることもあります。
価格帯の幅
- エントリーモデル(片耳5〜10万円程度)
- 基本的な機能を備えたモデルで、初めて補聴器を試す方に向いています。
- ミドルクラス(片耳10〜30万円程度)
- 雑音抑制や高度な音質調整機能を備えており、多くの環境で快適に使用可能です。
- ハイエンドモデル(片耳30万円以上)
- AI技術やBluetooth接続、充電式バッテリーなど最新の機能を搭載しています。
価格差の理由
- 技術と機能の違い
- 高度な処理能力や最新機能を持つ補聴器は、研究開発コストが高くなります。
- サービスとサポート
- 購入後のフィッティング調整やメンテナンスサービスも価格に含まれています。
注意点
- 安価な製品への注意
- 極端に安い製品は、医療機器としての基準を満たしていない場合があります。
どこで買えるのか
耳鼻咽喉科クリニック
- 特徴
- 医師の診断を受けた上で、補聴器の選定とフィッティングが行われます。
- 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会が認定している、補聴器相談医が在籍している病院・クリニックを選ぶと良いでしょう。コチラで公開されています。
- メリット
- 難聴の原因を正確に診断し、適切な治療と補聴器選びが可能です。
認定補聴器専門店
- 特徴
- 認定補聴器技能者が在籍し、専門的なフィッティングやアフターサービスが受けられます。
- 認定補聴器技能者がいる補聴器店はコチラから検索できます。
- メリット
- 高度な専門知識と技術で、最適な補聴器を提案してくれます。
眼鏡店・家電量販店
- 特徴
- 一部の店舗では、補聴器専門コーナーを設置し、専門スタッフが対応します。
- メリット
- 気軽に立ち寄りやすく、多くの製品を比較できます。
- 注意点
- 専門スタッフの技術や知識が、認定補聴器専門店と比べて劣る場合があり、適切なフィッティングが受けられないこともあります。
補助金について
身体障害者手帳による補助
- 対象者
- 一定の聴力レベルを満たし、身体障害者手帳を取得した方。
- 補助内容
- 補聴器の購入費用の一部または全額が公的補助されます。
- 手続き
- 市区町村の福祉窓口で申請し、医師の意見書や見積書が必要です。
自治体独自の補助制度
- 内容
- 一部の自治体では、身体障害者手帳がなくても補助金制度を設けている場合があります。
- 確認方法
- お住まいの自治体の福祉課や保健センターにお問い合わせください。
まとめ
補聴器は、医療機器として厳しい基準を満たし、専門家のサポートのもと個々の聴力に合わせて調整されることで、効果的に難聴をサポートします。集音器とは目的や機能が異なり、混同しないよう注意が必要です。また、補聴器の価格には技術やサービスの違いが反映されており、ご自身のニーズに合った製品を選ぶことが重要です。ご自身に合った最適な補聴器を選ぶことで、日常のコミュニケーションがより円滑になります。まずは専門家に相談し、一歩踏み出してみてはいかがでしょうか。
参考情報